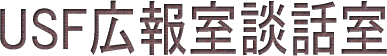
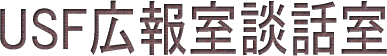
『銀河系大戦史』『猫屋版・銀英伝』に関する談話室
> 帰宅途中に「亜欧州大戦記」8巻を目撃したので購入してきました。
にやり……
でも「ジャ○アント・ロ○」は実写版しか見たことがなんですよね(歳がバレル!)
失礼しました。
もし不愉快な発言だと思われたら、削除してくださって結構です。
それでは。
> 零戦の悲劇
はやり2千馬力級のエンジン開発に手間取ったことと翼面荷重に
こだわりすぎたことが遂に後継機を生み出せなかった大きな要因
だったのでしょうが。
>3式弾はエリアウェポン
4年程前でしたか、PC98用のゲームソフトで「激闘!ソロモン
海戦史」というタイトルがありまして、一時期ハマったことがあった
のですが、このゲームのミッションで「夜間にアンダーソン飛行場に
接近し、艦砲射撃を行う」というのがありました。
3式弾は絶大なる効果を上げまして、それ以後、私としては3式弾
はエリアウェポンであると思っております。
#あのゲームは面白かった・・・。「大和」「武蔵」は被害担当艦
#扱いでしたが頑丈なの何のって。まさに「浮沈艦」でした。
#WIN版で出てくれないかな、と切に思います。
> A巻義O氏の文章技法
人、それを「御都合主義」と呼ぶのですけどめくるめく新兵器に
心奪われている人々にはどうでもいいことなんでしょうね。
#でも私みたいに狭量な人間は「そりゃないでしょう」とツッコミ
#を入れたくなるのです。
「ドキュメント太平洋戦争」、ざっと目を通したのですが資料が
きちんと分析してあって読みやすいですね。熟読してから感想
書かないと猫屋氏に笑われそうですので(笑)、感想は週末に
カキコすることにします。
ちょっと夏バテ気味で思考力も落ちてるようで、新しい話題が
出せなくて申し訳ないです。
それでは、また明晩。
>> ゼロ戦と3式弾は画期的?
零戦の悲劇は、まさにそこですね。改良できなかったこと。英国のスピット
ファイアは、大戦終了まで改良に改良を重ねられて使い続けられていた…と、
何かの文献で読みましたから。
改良するためにはぎりぎりの設計でありすぎたこと。改良したくても、それに
必要な技術力と資材が伴わなかったことでしょう。これも経済力・国力に帰す
る問題です。
>3式弾にしても手動で発射後何秒で破裂するか調節してやらねばならない弾頭
>だった訳で、戦闘中射撃速度が落ちるような弾頭を画期的と呼ぶのはどうかと。
三式弾は、陸上目標のエリア・ウェポンだと思っています。対空火器としては、
合衆国の開発したVT信管の足元にも及ばない。一分間に15発以上を発射できる
合衆国の5インチ両用砲と一分間に一斉射半の14〜18インチ砲では、対空火器
としての優劣は机上で明白。時速500キロのプロペラ機が一秒間に140メートル
移動する。ゆえに、14〜18インチ砲が一発撃って、次の一発を撃つまでに5.6
キロ動く。この移動量に伴う射撃諸元の急激な変化を、戦艦主砲の射撃装置が
追い切れたわけはない……と思いますね。VT信管をつけた三式弾は無敵だった
かも知れないけれど、今度はVT信管を1940年代の日本が開発できたか、という
命題に陥ってしまう。
>#A巻義O氏の仮想戦記なんて新兵器のオンパレードだけど、
>#「その兵器って、いつ慣熟訓練したんですか?」って質問
>#されたら即アウトですよ。あ、それは言わない約束?(笑)
後世世界だから、実際にはあり得ないようなことも当然のように起こるのであ
る(爆笑)。
#すばらしい一人ボケ・一人つっこみの文章技法だ、さすがです、A巻義O先
#生。
> 戦略について
猫屋さんの仰った「政略>戦略>戦術」の方が役割が判りやすいですね。今度、人に説明する時はこっちで説明します(笑)
> 新兵器に依存した仮想戦記
近代戦において、戦略レベルで完敗しながらそれを戦術レベルで
覆すのはほぼ無理です。それこそ核ミサイルでも敵首都に打ちこみ
でもしない限り。
何故なら政府首脳陣が戦場に出てくることはまずないからです。
ですので、新兵器に依存する仮想戦記は少なくとも近代戦以降は
無理なんじゃないかと思い、読む気がしません。
#A巻義O氏の仮想戦記なんて新兵器のオンパレードだけど、
#「その兵器って、いつ慣熟訓練したんですか?」って質問
#されたら即アウトですよ。あ、それは言わない約束?(笑)
> 戦艦空母とか潜水戦艦とか
まんま松本零二氏か小松崎茂氏の世界というか(笑)。
#馬鹿馬鹿しくって笑えますけど。
> 「歴史と経済まで考えた話が好き」
私も同じ考えです。でも正史の方における経済活動の実態とか
を正確に把握していないので騙されているかもしれない、と思う
ことはあります。
#それが「思わずニヤリとさせられる所」なんですけどね。
> 青木基行氏
「先生」と呼ぶと恥ずかしがる方だそうで。
7/27頃、「亜欧州大戦記」の8巻が発売されるそうです。
#とある掲示板にご本人がそう記されてました。
それでは、また明晩参ります。
おふたりとも、「そんな馬鹿な…」と思わせる政戦略の枠組みや1930〜40年代
の日本の経済力・技術力への仮定が少ないのが魅力ですね。つまりは、「歴史
と経済までしっかり考えた話が好き」という猫屋の好みに合致したということ
でしょう。
似たようなタイプとして、檜山良昭氏や、佐藤大輔氏の著作も結構読んでいます。
決して、この二方以外の物は読まないというわけじゃないです。多分、そういう
「好みに合う作家サン」が出てきたら、一も二もなくはまるでしょうね。
機銃の発射音「ドガガガガガ……」だけで丸2ページ使ったり、やたらと『戦艦
空母』を繰り出してきたりする方々のはちょっと……(一応、立ち読みしてみて
たりはする)。
>ここでちょっと質問があります。
猫屋は一応、政略・戦略・戦術に分けて考えています。手塚さんの考える戦略
は、猫屋の考える政略+戦略とおぼイコールだと思います。その意味で、わた
しも戦略転換は大小の歴史フレームの改編を引き起こすと考えています。
銀英伝だったと思いますが、「どの山に登るかを決めるのが政略、上るルート
を決めるのが戦略、決められたルートを手際よく上るのが戦術」という言葉が
ありました。国家の経営方針は政略に類するもので、極端な話を…本当に極端
な話…どの国と戦争をするのかを決めるのが政略になると考えています。戦略
は、政略の定めた目標…戦争相手…をどう打倒するかですね。無論、戦略を変
えれば、武器装備、訓練から戦場の選択、戦い方まで全部変わるわけです。戦
略転換が歴史の改編をもたらすのは無論のことです。ただ、それは政略で定め
られた、より大きな歴史のフレームに比べれば、影響範囲は比較的小さいとも
言えます。
とは言っても、政略・戦略で完勝しても、戦術で負けてしまって、結果的に歴
史のフレーム全体が変わってしまうということも皆無とは言えない。完成度の
高い新兵器によって戦術レベルでの逆転が起こり、結果的に歴史そのものが変
わる可能性こそが『新兵器に依存した仮想戦記』の生きる道でしょうね。
> 『混沌の薄明』刷り上がりました
> 「日本の敗因」角川書店刊
情報ありがとうございます。全巻、面白そうな内容ですね。早速図書館で調べてみます。
#すぐに書店で購入と言わないところに貧乏性が出てます(笑)。
> 仮想戦史=ファンタジー?
これは私もそう思います。いや、SFかもしれませんが。
ここでちょっと質問があります。
No.35の発言で「歴史改編」と「戦略転換」を分けているように取れるのですが、戦略転換=歴史改編になるのでは?
#「戦略」というのは、大雑把に言えば「国の経営方針」ですよね?私はそう考えているのですけど。
ついでにもう1つ質問。
横山信義氏と青木基行氏の著作のみ読まれる理由は何ですか?
> ゼロ戦と3式弾は画期的?
ゼロ戦に関しては史上初の戦略戦闘機としての意義は大きいと思います。ただ、構造上の欠点(主に防御力の低さ)を改良していくことの
できなかった所に悲劇がありますよね。
3式弾にしても手動で発射後何秒で破裂するか調節してやらねばならない弾頭だった訳で、戦闘中射撃速度が落ちるような弾頭を画期的と呼ぶ
のはどうかと。
続きは今夜、書きこませていただきます。
では。
今日、届いちゃいました。
>どういう内容だったのか、教えていただけると議論できそうですが。
角川文庫、平成7年初版です。ざっと内容を紹介すると…
1. 1940年当時の日本のシーレーン防禦の脆弱さの研究
副題が『日米開戦 勝算なし』。いきなり、結構な辛辣さです。
2. 日本と合衆国間の戦術思想の落差の研究。日本の軍隊を『学ばざる軍隊』と表
現する、かなり辛辣な内容に驚きました。
3. 電子兵器と用兵思想の落差に関する研究。ご存じVT雷管の登場にまつわる内
容です。
4. 日本的の軍隊での責任論インパール作戦を、兵站面、組織での責任体制、
英軍との戦術比較から紹介しています。
5. いわゆる「共栄圏」の実現可否に関する研究。
『南方資源地帯』へ進出することで、日本は資源を手に入れたわけです。しか
しながら、『南方資源地帯』は無人の野原ではなく、多くの人口を擁する、欧
米の植民地だったわけです。これらの植民地は欧米に『搾取』を受けていたわ
けですが、一応は、欧米諸国に一次産品を輸出し、見返りに…見返りとして十
分かどうかは別として…二次産品や教育、資本の提供を受けるという経済体制
の中にありました。欧米に取って代わったことで、日本は、これらの植民地に
対して二次産品を始めとする『見返り』の提供の義務を負ったわけですが、無
論のこと、当時の日本にはそんな充実した第二次産業も、投資するに十分な資
本力も、また、教育や文化の普及といったシステムもありませんでした。さら
にはシーレーン防衛能力の低さから、これら植民地間での輸送・連絡すらまま
ならなくなります。日本のみ良ければという観点に立った『収奪』は、『南方
資源地帯』そのものを荒廃させる「共貧圏」出現に繋っていきました……その
結果、これらの地帯の人心は日本から離れ、日本は戦争遂行のための地盤を足
下から、自分自身の手で掘り崩していった、といった内容です。