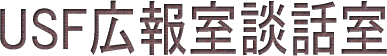
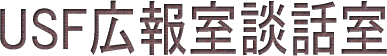
『銀河系大戦史』『猫屋版・銀英伝』に関する談話室
初めまして。
別途、メイルもさせていただきます。
銀英伝関係のHPを渡り歩いていて、イヌラーさんの所から
ここにこういう質問を書いていいものか、ちょっと気後れ
してしまいましたが、お返事頂ければ幸いですm(- -)m
8/13 東ム12bです。
いずれも原稿終了。入稿待ち
きつむらさん、いらっしゃいませ。リンクありがとうございました!
猫屋さま、初めて書き込みさせていただきます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
私も銀河系大戦史、こつこつ拝見させていただきますm(_ _)m
> ただそれにしても、早い段階で連邦市民にグランド・ヴィジョンを提示し
根回しはやっていますよ。とっても地道に(笑)。すでに『青き焔の輪』で「何をやっている」かを腹心にぽろっと漏らしてますし。
「およそ人間の才能で最も見いだしがたいものが軍事的才能である」というのが司馬遼太郎氏の言葉だったと記憶します(『花神』だったかな?)。大戦史の物語世界では、一応、軍事的な才能の有無は6歳〜15歳くらいまでに行う心理試験でおおよそ判定できるというご都合主義な設定になっています。一度は生母とともに捨て去ったはずのレーフラムを、ナイザルが無理矢理に引き取ったり、ストリート・ギャングだったアヴドーチャをアルドリースキー財団がスカウトしたり……といったエピソードの背景設定です。
でも、軍事的天才だけは『出てくるのを待つ』しかないんですよね。
> ところで、そういえば例の失言総理も一応「簒奪政権」ということになる
>のかな……何かやたらスケール小さいけど(爆)
あれは「纂奪」ではなくて、「棚ぼた」と言うのではないか、と? だから、政権の重みがわからなくてぽろぽろと失言を……
それと続いて高村さんへ
>フレーゲル男爵
憎んで憎んで、憎み抜いた挙句、相手への奇妙な理解に達してしまうというのは人の世の妙というものでしょうか。
もっともラインハルトからは終始、視野の外だった気もしますが(^-^A
しかし、若干26歳――貴族社会の敵という以外に、歴史の表舞台を一気に駆け上がってゆくラインハルトに対する、己が身の卑小さへの苛立ちというのもあったんでしょうな。
その意味で、フレーゲルが真に憎んでいたのはラインハルトでなく、彼の存在など簡単に圧し流さんとする「歴史」そのものであった……などと書くと、ちょっとかっこつけすぎですか(^o^A
>>アニメのキャラデザが悪すぎるのか…。
すっかり悪人面でしたからねぇ(-o-;;
ただ「敗者」からの視点というのも、歴史の見方を豊かにする大切な要素のひとつ。「敗者」の戦場での意地があったればこそ、「勝者」もまた戦後、「敗者」の気持ちに理解を巡らせる――まぁ、戦争なんかしなくとも理解し合えればそれに越したことはないんでしょうが。
でも歴史や政治の勉強をやっていて本当に味わい深いのは、こうした「敗者」の歴史だったりするのですけどね。
それでも、キャラ萌えから入った人には難しいのかなぁ(-o-ゞ
では、通販の件はメールにて改めて(^-^)/
あとこれは日記の方から。
>戦争のルール
純粋な戦死者の数ではWWIの方が多いのですけど、結局、国際システムがまともな戦争抑止の機能を獲得したのは、無数の市民に犠牲を出して、戦略爆撃と核による相互確証破壊(MAD)が確立したWWII以降のことですしね。
ある意味、それまで人類は真剣に「外交」というものを考えようとしてこなかったとも言えるわけで、身近に踏み込んでこない限り、「戦争」を市民感覚で捉えるのは難しいのかもしれません。
そういえば、この時代のマスコミは「戦場映像」をどこまで報道してしてるんでしょうか? 比較的、報道管制のやりやすそうな戦争形態ではありますが。
その他の話題については、おいおい、ということで。
どうも、猫屋さん
>>マールクの戦略的天才への読み違い
あとミットリッフェル会戦に関しては、マールクの才能を支える艦隊将兵の層の厚みと艦隊運用ソフトウェアの質の高さも読み違えのひとつでしょうね。レーフラムの作戦案に目を通して、あそこから押し返せるだなんて、なまじ軍事知識のある人間ほど予想がつきません。通信回線を破壊された宇宙艦隊がまがりなりにも艦隊運動を維持できるだなんて、連邦空軍の水準では理解の外でしょう(^-^;;
同様にヒューレルの過大評価というのも、大戦勃発以前のまっとうな軍事エリート・コース出のナイザルに見抜けというのも難しかったのかも知れませんね。軍事的才能というやつばかりは、実戦にさらされなければ判らないものですし。
レーフルの評価が遅れたというのは……まぁ、こればっかりは、ついこないだまで一介の戦闘機パイロットだったわけですから(^o^A
ところで、そういえば例の失言総理も一応「簒奪政権」ということになるのかな……何かやたらスケール小さいけど(爆)
はじめまして、義忠さま。
> その辺りの読みが当たっていたかどうか、夏の『銀の陥
まあ、失望はなさらないでしょう(^-^) 。その辺はお約束します(実は『白虹の宇宙』以来、久しぶりに自分の原稿を校正していて楽しかったので)。実に陰険な親父、いよいよ本領発揮か……というところですが、無論、すべてがすべてかの親父殿の思うがママに動くわけではないと言うのが歴史の面白いところとなるわけです。コーラルにはコーラルの意地もあり、シュレフにはシュレフなりの都合、ル・ヲント側にも言い分というものがありますからね。それらが絡み合いつつ、いったんは連邦と共和国に分離した物語が、次巻『銀の陥穽』末尾で合流します。どのように合流するのか……は、読んでのお楽しみ(^_^)/